|
|
| 青 木: |
四万十川の岸辺の家での生活はとても苦しかったです。父は農業を嫌いました。母も町の育ちの人で元教員でしたから、農業が好きじゃなくて。だから、両親は結局、私が10歳のとき高知市に出ることになりました。そのときもずっと父の暴力は続いていました。全部自分のストレスの捌け口ですからね。 |
| 箱 崎 : |
具体的にはどういう暴力が一番きつかったですか? |
| 青 木: |
そうですね、やっぱり一番怖かったのは蹴られるときですかね。胸をけられるときは反射的に防ぐんですけれどね。あと、拳固もすごく痛かったです。父は何ていったって元は職業軍人ですからね。父に蹴られて倒れてひどいときはタンスの角に頭をぶつけて、ここに傷があるんですけどね。そういうとき、頭っていうのはすごく血が出るんですよね。そうするとね、それを見た父は、目が覚めたように真顔になって、私を連れて病院に走るんですよ。 |
| 箱 崎: |
自分でやっておきながらっていう感じですね。 |
| 青 木: |
そう。だからね、病院の人たちは、優しいお父さんだと思っていて。今だったら、きっと「これは虐待じゃないか」と思うかもしれないんですけど、昔は全然でした。私も「父にやられた」なんて一言も言いませんから。絶対黙っていますしね。普通に傷の手当してもらって病院から帰ってくる。そのときは結構父も優しいんですよね。でも、一日ぐらいしか続かないんですよ。またすぐにカァーっとなってしまう。とにかく父がお酒を飲む場面がすごく嫌でしたね。これから酒になるなと思うと、警戒心というか、自分の中の信号が鳴り始めて。だから、裏表なんですね、優しいようなのと。でも本当の優しさじゃないんですけどね。いつもそうことが子どもの私を混乱させましたね。 |
| 箱 崎: |
何事もなかったかのように…という感じですね。 |
| 青 木: |
そうなんです。 |
| 箱 崎: |
昨日のあれは何だったみたいな感じなんですね。 |
| 青 木: |
そうです。だから、自分の中で、あれはなかったことなんだって思うときもあったんですよ。でも、やっぱり痛みは残ってますしね。すぐには消えませんし。傷も残っているし、あったんだと思うんだけど、また次の瞬間には、あれはなかったことなんだと思いたい。。 |
| 箱 崎: |
そういう毎日だと本当に混乱して、何が起こったか分からないという感じですね。 |
| 青 木: |
本当にそうなんですよ。それで、今から思うとすごく怖いのは、ほかのことが全然ちゃんと落ち着いて認知されていかないんですよ。
たとえば、今日は小学校の遠足だとか、子どもの思い出っていうのがありますでしょう、刻まれていく。それがほとんどないんですよ。もう、どうやって殴られないようにするかとか、そんな思いばっかりだから、記憶の順番が、体に刻まれたその暴力の方が1番であって、2番目が学校とか幼稚園で体験した思い出っていう感じなんですね。
だから、自分が楽しかったはずの子ども時代というのにすごくベールがかかったような、それは何かつけ足しみたいな、お芝居のような気がどうしてもするんですよ。私にとっての現実は、やっぱりあの恐怖心と痛かったこと、怖かったこと、そっちの方が1番で。だから、自分をうまくまとめていく時期、思春期のころは本当にしんどかったですね。 |
| |
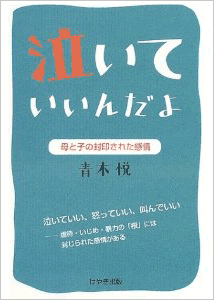 |


 |気づきの対話
top|
|気づきの対話
top|