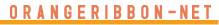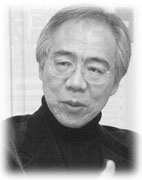|
〈親子になる〉というモチーフは新鮮だ。実親と実子の関係では、〈親子になる〉という
プロセスは省略されるか隠されている。はじめから〈親子である〉ところから出発する、そのようにみえる。
したがって、前回記した「見せかけの時期」は実親と実子の関係においてはないようにみえる。これから紹介したいと考えている「試しの時期」も通過しないように思える。
けれどほんとうに血のつながった親子関係にこれらの時期はないのだろうか。ことによると、実親と実子の関係では母子間の愛着関係があまりに早期において、それも短期間で成立してしまうため、それが〈親子になる〉プロセスであることを自覚できないだけなのではないか、養子を迎え入れるプロセスを知ると、そんなふうに思えてしかたない。今回はこのあたりのことを探ってみたい。(*)
子どもという存在の基本的なあり方をイノセンスという言葉でとらえてきた。子どもは自己という存在の誕生に何一つ関与していない。関与できなかった。すなわちこのいのち、このからだ、この性、この親・・・すべては強制的に贈与されたものであって、何一つ選んでいない。つまり根源的受動性としてこの世界に出現してきたからである。
したがって自分という存在をめぐるこれらすべてを受けとめることができない。どう受けとめていいかもわからない。この受けとめられない状態、受けとめ切れない現実をイノセンスという言葉で言い表してきた。こう言い換えることができる。子どもは自分という存在をめぐるこれらすべてに対して責任がない。イノセンスは自分に対して、責任がないという意味でもある。
したがってイノセンスという状態は、受けとめられ欲求として表出される。イノセンスの表出は、受けとめられたいという欲求である。
赤ちゃんを目の前につくづく実感するのは、子どもという存在がイノセンスそのものだということだ。同時に赤ちゃんは生きて今ここに存在していること自体において、イノセンスの表出態そのものでもある。受けとめられなければ、自分という存在を維持できない。
赤ちゃんは、最初の生の意欲を、受けとめられ欲求として表出しているのである。
言い換えれば、子どもという存在はイノセンスであり、イノセンスの表出態である。イノセンスは必ず表出される。表出されたイノセンスは優先的にかつ無条件に受けとめられなければならない。なぜなら子どもが自分という存在を自ら受けとめることができるようになるためには、受けとめ手により受けとめられたという体験を不可欠としているからである。
(次ページへ) |
 |