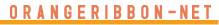|
続き4・・・
岩崎さんは、〈親子になる〉ステップの第一歩が見せかけの時期だと述べる。なぜ子ども
はすぐに見せかけの自分を脱ぎ捨てないのだろうか。
施設においても「いい子」、里親の家においても「いい子」。場所を違えた「いい子」の 反復は同じ見せかけであっても、その意味は異なっているはずだ。施設における「いい子」
は生きのびるための方途であった。では里親の家における、まるで小さなお客様のような 「いい子」の意味はなにか? まずはこれから親子になろうとする者同士の初めての水入
らず、それゆえの双方のぎこちなさに、どのように自分を表していいかわからない、だか ら「いい子」としての振る舞いは戸惑いの表現という解釈ができるだろう。
岩崎さんは、いつまでも「いい子」が続いているのなら、子どもの心に、この人たちは うっかりと心を許したりしては駄目なのだと思われていることになる、と述べている。な
るほど、と思う。子どもが里親に心を許し、緊張を解くための期間ということなのかと納 得する。
見極めといってみる。この後に続く試しの時期、そこで子どもが起こす激烈な退行現象、
それは試しの行動(リミットテスト)と名づけられているのだが、試しの行動は、受けとめ
手を得てはじめて表出が可能になる。この人たちは自分だけの特定の永続的な受けとめ手
になってくれるだろうか、子どもはごく短期の間に、その判断をくださなくてはならない。
もっと積極的には、是が非でも受けとめ手になってもらわなければならない。そのために
は「いい子」として振る舞い、彼らから自分への肯定性を引き出す必要がある。見せかけ
の時期に子どもが遂行しようとしたことはこのような切実きわまる課題ではなかったろう
か。(第3回目 了)
(注1) 私の知るかぎり、この協会以上に、施設から家庭へという環境の激変過程を子どもに添うようにして、「親子になる」(里親―里子)という視点から丹念に言葉にしてみせたところはない。
(注2) この時期で手こずることがあるとすれば、せいぜい入浴のときぐらいなものだ。特に乳児や幼児では、施設での入浴で大人の裸を見たことがないので驚いて泣くことがあるけれど、一、二回泣けば、大丈夫、お風呂が大好きになると岩崎さんは記している。
(注3) きまりやシステムが養育を代位する施設は、きまりやシステムを守らせられなくなったとき、崩壊する。子どもたちはむき出しの欲望を前面に出し始める。力の強い子どもが跋扈(ばっこ)し、弱い子どもは食事さえろくに得ることができないという暴力支配の無法状態が出現する。受けとめ手が不在であったことが露出するのだ。
(注4)〈親子になる〉というモチーフは新鮮だ。一般家庭では、〈親子になる〉というプロセスは省略されるか隠されている。はじめから〈親子である〉ところから出発する。
|
 |