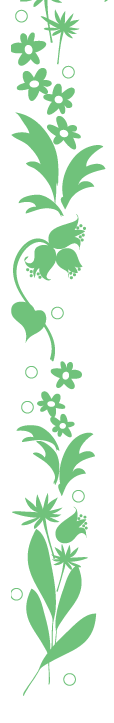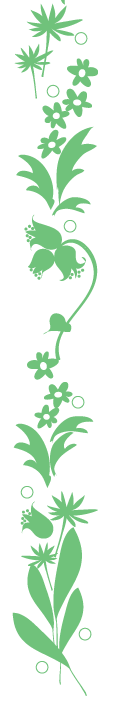・・続き2
当時の私は、自分の姉たちも含め周囲の子ども達が自我丸出しで大人に逆らい叱られ罰を受ける姿を見て「なんてバカなんだろう」と、心の中でせせら笑っているような嫌らしい子どもであった。
また、休日など無い父に一度も遊んでもらったことのない私は、周りの子どもたちのなかでも酷くスポーツが苦手で、体を動かすことに関しては何をやっても最低だった。心の中は捻くれて、スポーツでも全く良いところがなかった私だったが、母とその先生はそんな私の良いところを(殆ど無理やり)見つけ出し、いつも褒めてくれた。
例えば、学校のマラソン大会で文句なしの最下位になると、それについて母が作文を書くように勧めてくれ、その作文を先生が褒めてくれるというようなこともあった。
母は、今考えても笑ってしまうほど盲目的に私を愛し、その先生は「笑顔がとても素敵」など全く持って主観的で根拠の無いことで私を褒めてくれた。それは私の成績が良いからでも、運動が得意だからでもなく、私が私そのままであることを褒めてくれたのだと今では理解できる。この経験により、私は今日まで自分を好きでいることができているのかもしれない。
●いじめがあった千葉での暮らし
次の千葉県に引っ越してからの生活は、山の中しか知らなかった私にとって、本当につらいものだった。当時の私の作文や学校に提出した絵日記などを見ると、私の歪みかけた発達がはっきりと表れている。その時の私は明らかに環境の変化についていけていなかったようだ。
当時の私にとって最も大きな変化は、母との関係であった。それまでは、牧師の妻として陰で教会と牧師を支えることが主な役割で、子どもと関わる時間を十分に確保できていた母は、幼児園を併設している新しい赴任先での役割の多さに、子どもとの関わりどころか家事さえままならない状態になっていた。
それまでの居場所を失い、精神的な拠り所であった母にもゆとりがなくなったことで、結果的に私は不安定な状態に追い込まれてしまっていたようだ。爪を噛む癖が始まり、血が滲んでもやめられず、沖縄に転居するまで一度も爪切りを使うことはなかった。
学校や家で絵を描いても、一本の線で描くことができず、震えるような細かい線をつなげて描いていた。学校の先生にとっても、私は扱いにくい子どもだったに違いない。実際、クラスでは大騒ぎをして授業を崩壊させ、作文には平気で「担任は他の先生の方がよかったのに・・・」と書いていた。
そしてその不安定な状況のなかで、アイデンティティについての悩みが再び私を支配するようになっていた。「僕は誰で、どこから来てどこへ行くのか」という問いに答えを見いだせず、恐怖にも似た苦しみの中で、誰にもその悩みを打ち明けられずにいた。小学生の私からすると、周囲の大人も子どもも、『自分が誰なのか』など気にも留めずに過ごしている間抜けにしか見えなかった。
(次へ続く→)
|