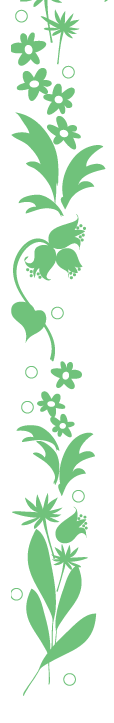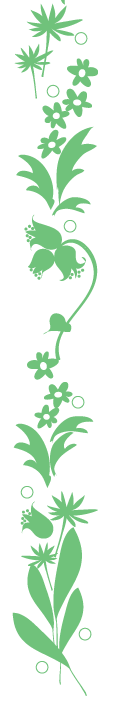ロンドンの小児病院に留学した1960年代初めも、イギリスで子ども虐待は多発し始めていた。子ども虐待を専門にしている病院の心理学者が私に、「日本では子どもをおんぶする習慣があるそうだが」と話しかけてきた。「日本も豊かになって、今は乳母車に乗せるようになっている」と返事をしたところ、彼は「それは残念だ、おんぶは母と子のスキンシップの面積が大きく、相互作用の強い子育てのやり方だ」と言った。
「おんぶ」にしろ、「だっこ」にしろ、スキンシップを介して、母と子はふれ合うことによって、お互いの愛情を確かめ合いながら、母と子の心の絆はつくられていくものであるが、そのとき、それが虐待問題の予防につながることに気付かなかった。当時私の関心は、子どもの腎炎の免疫病理学的なメカニズムを明らかにすることに向かっていたからである。
私が、日本で初めて「子ども虐待」の事例をみたのは、東大小児科の教授になってからである。虐待といっても特殊な事例で、熱い煮え湯を飲まされた赤ちゃんであった。母親は下町の美人という感じの静かな女性で、1970年のことであった。
わが国でも、1960年の終わり頃から、小児科医、また児童精神科医からも、子ども虐待のひとつである「ネグレクト」の症例報告が出始めた。アメリカの身体的虐待である“Battered
Child Syndromeモ ではなく、小児科学的に見ると「情緒(母性)剥奪症候群」と呼ばれる病型から、わが国の子ども虐待の医学研究は始まったと言える。
しかし、戦後の混乱期には、貧困であるが故に、「捨子」、「子殺し」、「コインロッカー事件」などいろいろな形の貧困型社会の虐待は存在していた。また、厚生省(当時)児童家庭局は、児童相談所でみられる相談事例の中の特殊な事例をあつめて報告するという事業を、1950年頃より始めていたが、初めは散見する程度の虐待事例であったものが、次第にその数は増加し、1980年代には、相談事例の約半数近くを占めるようになったという。したがって、わが国では、アメリカと逆で、福祉領域が、医療より先に、この問題に対応してきたと言える。
アメリカで見た子ども虐待事例の体験や、イギリスでの心理学者とのやり取りから、また1970年代から始まる育児問題の多発を考え、育児の研究班を作るよう厚生省に働きかけ、1978年に「母子相互作用」の研究班を立ち上げた。母と子の絆は母と子のやりとりによって相互的におこるという理念が「母子相互作用」であるが、そこで、その欠如にも関係する子ども虐待が小児医療の現場でどの程度起こっているかの調査も行った。最初の調査でわかったことは、驚いたことに、いわゆる子ども虐待は何十例という少ない数だったことである。しかし、子ども虐待の数は急速に増加し、現在、児童相談所の取り扱う数は、年間35,000例というが、注意すべきは、保育士、看護師、医師、教師などが見る、表に出ない事例もあるので、実数は児童相談所の事例数の1.5倍位と推定される。
1980年代から、子ども虐待問題をなんとかしなければという考えが、小児科医、児童精神科医の中で湧き上がり、国際的な影響もあって、1992年に「日本子どもの虐待防止研究会(JaSPCAN/現「日本子ども虐待防止学会」)が設立され、小林美智子先生、斉藤学先生の要請で会長を務めた。そして、第10回の研究会で学会に発展した機会に、理事長・会長を小林美智子先生にバトンタッチした。子ども虐待研究は、現代社会の最大のテーマであると考えている。(次へ続く→3)
|