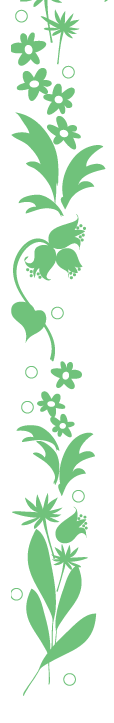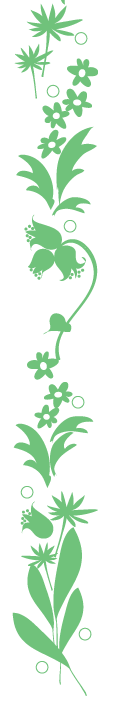(〜ライフストーリー続き)厳しい母のもと、今思うと軽い心身症ではなかったかと思うが、手が動かなかったりしたこともあったが、日曜学校の学生さん達と過ごす優しさ一杯の2時間は、厳しさに押しつぶされそうだった私の心を、充分に勇気づけてくれるものであった。余談だが、それから20有余年後のアメリカ留学の折に見たオハイオのカレッジが、同じように美しかったことも思い出す。
勿論、母も、厳しさの中に母としての優しさのある人であった。妹や弟が幼いころ、母が子守唄をきれいな声で歌っていたのを覚えている。きっと私にも同じように歌ってくれたのだろうと思う。
また、小学校高学年の頃、我が家にもクリスマスがあって、声楽を勉強していた母の妹が、当時結婚して旧満州に住み、そのころになると必ず送ってくれたロシア・チョコレートと、母からのクリスマス・プレゼントが恒例になっていた。
ある年のクリスマスの夜、母がちょうど小さなプレゼントを枕元に置いてくれたときにふと目が覚め、窓から差し込む月明かりに浮かんだ母の手が見えた。そのときのことは、今でも鮮明に思い出すことが出来る。
私が幼すぎて、母親の愛情を充分に理解出来ないでいたこともあっただろうと、今になると思う。この後家庭を離れて、海軍兵学校、第一高等学校、東大医学部に進み、アメリカ・イギリスへの留学も含めて、厳しい医師の道を歩むことになるが、どんなときにも、何とか乗り越えられたのは、私に向けた母の厳しさと暖かさのお蔭であると感謝している。そして又、私からも分るように、どんな子どもにとっても、成長過程で出会う親を含めた大人の存在は極めて重要なので、多くの幸せな出会いがあるよう願って止まない。(了)
|