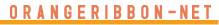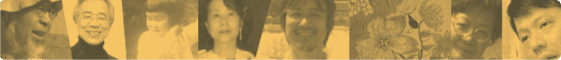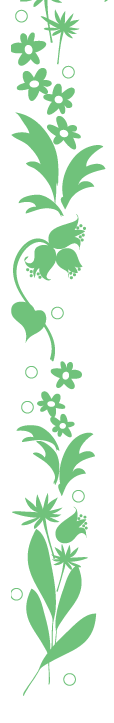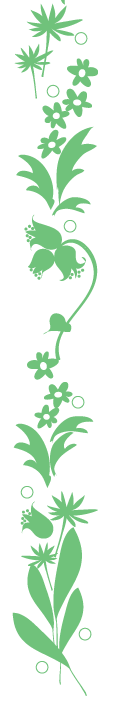けれども、記憶の断裂という言葉の裏には幼いながらも自分の心を守るという作用が働いていてそれらを消去してしまったのではないかと思っている。また、順応性も強かったのかもしれない。そうでなかったなら、それらの場面が鮮明な記憶として残っていたならば数々のトラウマを抱えて苦しみ、嘆き、世間を恨みといった最悪な人生となっていただろう。だから良い思い出の方が残っていて私の後半生を救ってくれている。(カウンセリングを受けに来た子ども達の何人かは、母親が妹を出産する前後に親戚に預けられた時とか、冷たい視線を向けられたなどの記憶が残っていて疎外感を感じたり、自分は必要とされてない存在だという思いを引きずっていた。)
アン基金プロジェクト発行の里親シリーズの「今が春よ!」で私の自分史を紹介しているが、母の離婚後に預けられた米国人家庭で充分に愛された思いは、ひと月足らずという期間だったが心に刻印され、その後の歩みを示してくれた。
母の離婚、再婚による異父妹の誕生など家族の離散や変動の経験は血族に固執しない感覚をもたらし、結婚して2児の母となってからの歩みは、オープンな家庭として里子や米国人学生のホームステイ、不登校や引きこもりなどの子どもたちを引き受けて過ごす年月となった。
デラシネという言葉に戻るが、結婚して家庭を持ってからも夫の転勤などに従って7回転居しているし、8年前からは東京の家族から離れて単身で群馬の山中に移り住んでいる現在までを数えれば20数回余りの変転ぶりである。デラシネという言葉を辞書でひけば、根無し草とか故郷を喪失した者という。確かに石川県で生を受けたが、1歳で東京に移った者には故郷という感覚はないし、その後の変転ぶりは根無し草のように一箇所にとどまらない暮らし振りだった。だから私はデラシネの民なのだろう。しかし、この言葉にともなう悲しみや寂しさは今の私にはない。どのように変転しても私は日本の中をちょこちょこと動いただけなのだから、人は認めないだろうし、海外に住んだ訳でもないけれど、私の故郷は日本だと開き直って思うようにしている。それを後押しするように、今年の夏に聞いた言葉に私の心は落ち着いた。
それは、里子として育てた娘が私のいる群馬の地を人に「実家」に行くと言って訪ねだしていることだ。私がどこに移ろうが共に過ごした思い出を抱いて彼女は私の存在を実家と言う。親達に置き去りにされて我が家に移って暮らし、その後転々とした年月の末に自分の実家と定めた彼女の自在さに学んだ。
彼女もデラシネの民。デラシネの民にはしたたかで自由な発想と自在さがある。(了)
|